今日から使える行動支援の基本
問題の本質
子どもの「困った行動」は、意志や性格の問題ではなく、環境との相互作用で起きている。
今日できる最小アクション
行動の「前後」を観察し、1つだけ環境を変えてみる。
得られる変化のイメージ
「どうしてできないの?」から「どう環境を整えればできるか?」へ、視点が変わる。
応用行動分析(ABA)って、どんな意味?
応用行動分析(ABA:Applied Behavior Analysis)とは、行動の前後に何があるかを観察し、環境を調整することで行動を変える科学的手法です。
わかりやすく例えると、こんなイメージです。
× 「ちゃんとしなさい」と気持ちで押す
◯ 「できる仕組み」を環境に埋め込む
子どもが朝の支度でつまずくとき、ABAでは「やる気がない」とは考えません。
「視覚情報が多すぎて混乱している」「次にやることが見えていない」など、環境側に摩擦があると捉えます。
なぜ行動が止まるのか?脳と環境の”摩擦”
人間の脳は、目の前の刺激に反応するようにできています。
- おもちゃが目に入る → 触りたくなる
- 次の予定が見えない → 不安で動けない
- 成功体験がない → やりたくない
ABAでは、この「行動の前(きっかけ)」と「行動の後(結果)」を整えることで、自然と望ましい行動が増えるよう設計します。
特に発達に凸凹のある子どもは、感覚の受け取り方や情報処理に独自のパターンがあります。
だからこそ、その子に合った環境設定が、何よりの支援になるのです。

環境デザインのチェックリスト
ABAの視点で環境を見直すとき、以下の4つの軸で整理します。
✓ 物理的環境
- 目に入る情報量は適切か(視界に余計なものがないか)
- 刺激が強すぎる音・光・におい はないか
- 動線に「迷うポイント」はないか
✓ 前後の動線
- 次にやることが見えているか
- 終わりのタイミングが予測できるか
- 切り替えのための「間」があるか
✓ 感覚への配慮
- 触覚・聴覚の負担が大きくないか
- 疲れやすい時間帯ではないか
- 落ち着ける「逃げ場所」があるか
✓ 成功の設計
- スモールステップになっているか
- できたら「何が得られる」かが明確か
- 失敗しても再挑戦できる仕組みか
仕組み化テンプレート(どのテーマにも応用可能)
ABAを家庭で取り入れるとき、以下の3つの柱で組み立てると実践しやすくなります。
1. 固定ルーティン
毎日同じ流れ・同じ順番にすることで、脳の負担を減らす。
例:
- 朝は「起床→トイレ→着替え→朝食」
- 帰宅後は「手洗い→おやつ→宿題」
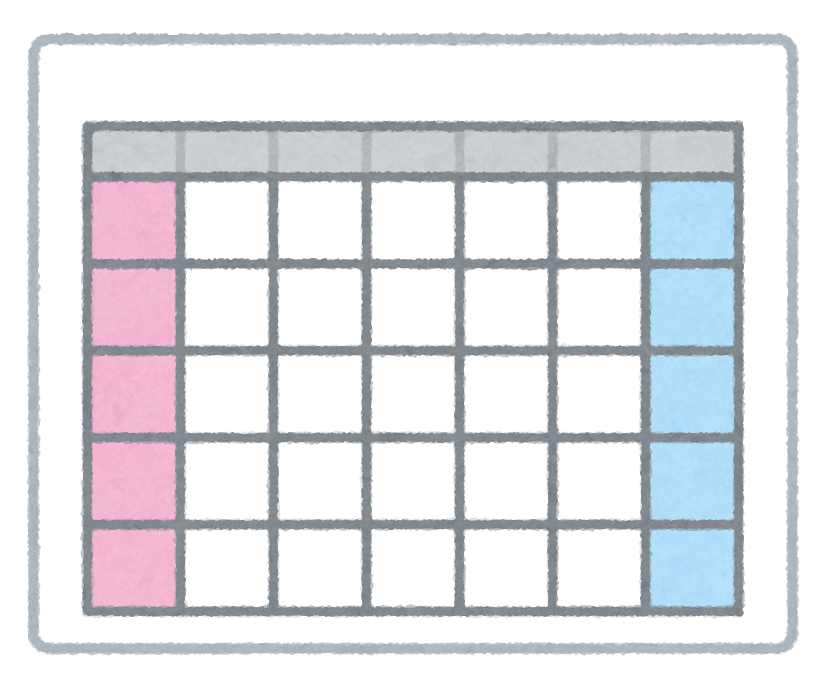
2. 可視化ツール
目で見てわかる仕組みをつくる。
- タイマーで「あと◯分」を見える化
- 写真カードで次の行動を予告
- チェックリストで「終わった感」を作る
3. 家庭内ロール分担
誰が・何を・いつするかを明確にする。
- 親が毎回指示を出さなくても回る仕組み
- 「見守り役」と「誘導役」を決める
- きょうだいがいる場合は役割を可視化
よくある失敗 → 改善ポイント
❌ NG:毎回口頭で指示を出す
→ ◯ OK:視覚支援で「見ればわかる」状態にする
子どもが覚えていないのは、記憶力の問題ではなく 情報の受け取り方の特性 です。
イラストや写真で手順を掲示するだけで、自発的に動けるようになることも。
❌ NG:「できたらご褒美」だけで終わる
→ ◯ OK:「できた」という体験そのものを積み重ねる設計にする
短期的なご褒美も有効ですが、長期的には 「自分でできた」という達成感 が行動を支えます。
成功体験を小さく刻み、積み上げられる環境をつくりましょう。
❌ NG:一度にたくさん変える
→ ◯ OK:1つだけ変えて、効果を観察する
ABAの基本は 「測定と調整」 です。
複数の変更を同時に行うと、何が効いたのかわからなくなります。

個々の特性による”設定値”調整
ABAでは、子ども一人ひとりを 「環境パラメータが異なる個体」 として捉えます。
感覚過敏がある場合
- 音・光・触覚の刺激を減らす
- イヤーマフ、サングラス、タグなし衣類などを活用
- 刺激が多い時間帯を避ける
疲れやすい・切り替えが苦手な場合
- 活動と休憩のセットを短く設計
- タイマーや音で「終わり」を明確に
- 次の活動の予告を早めに入れる
こだわりが強い場合
- ルーティンの「型」を尊重しつつ、少しずつ拡張
- 選択肢を2〜3つに絞る
- 変更は予告+視覚支援で事前に伝える
5分スターター:今日からできる最小の一歩
1. 1つの行動を「3つの視点」で観察する
- 行動の前に何があったか?
- 行動の後に何が起きたか?
- その結果、行動は増えたか・減ったか?
2. 1つだけ環境を変えてみる
- 視界に入るものを減らす
- 次の行動を写真で予告する
- 終わりのタイマーをセットする
3. できたことを記録する(小さくてOK)
- 「1人で靴を履けた」
- 「タイマーを見て切り替えられた」
- 「カードを見て次の行動ができた」
4. 家族で「誰が何をするか」を1つ決める
- 「朝の支度は◯◯が見守る」
- 「タイマーセットは△△がやる」
5. 1週間続けて、変化をメモする
- うまくいった環境設定
- まだ摩擦がある場面
- 次に調整したいポイント
まとめ:行動は”仕組み”で支えられる
応用行動分析(ABA)は、「できない子」を「できる子」に変える魔法ではありません。
そうではなく、「その子がその環境で、自然とできるようになる仕組み」を設計する科学です。
大切なのは、
- 行動の前後を観察すること
- 環境を少しずつ調整すること
- 小さな成功体験を積み重ねること
今日から、1つだけ環境を変えてみてください。
それが、子どもの「できた」を増やす第一歩になります。
▼ 背景の”心の動き”は、無料noteでやさしく解説
子どもの行動の背景にある 感情・不安・認知のプロセス を、発達心理学の視点からやさしく解説しています。
▼ 年齢別・場面別の声かけ台本と記録シート完全版はメンバー向けで配信中
『ゆうたまの発達支援ラボ』では、
- 年齢別(2歳〜小学生)の具体的な声かけ台本
- 場面別(朝・夜・外出・宿題)のフローチャート
を配信しています。
この記事が少しでも参考になったら、ぜひシェアしてください。
一人でも多くの保護者・支援者に届きますように。

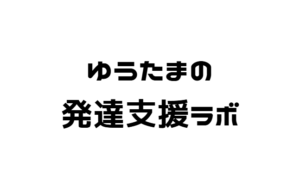
コメント