この記事はこんな悩みを持つ方へ
- 初めて管理職になり、年上の部下との接し方に悩んでいる方
- 年上部下への指示出しに気を遣いすぎて、仕事が進まない方
- 年上部下から反発されたり、距離を感じている管理職の方
- リーダーシップと人間関係のバランスに苦しんでいる方
- 「偉くなった」と勘違いしてしまい、部下との関係がギクシャクしている方
このような悩みを抱える管理職の方に向けて、児童福祉系の会社で働く私、のすけ自身の失敗と成功の体験から学んだ「年上部下と良好な関係を築きながら、組織の成果も出す方法」をお伝えします。
年上部下との関係構築は、多くの管理職が一度は通る「壁」です。私も何度も失敗し、悩み、試行錯誤を重ねてきました。この記事では、その生々しい体験と、実際に効果があった具体的な方法を包み隠さずシェアします。
のすけが年上部下との関係で失敗した理由
はじめまして、のすけと申します。私は現在、児童福祉系の会社で管理的な立場を任されています。子どもたちの未来を支える大切な仕事に携わっており、やりがいを感じながら日々業務に取り組んでいます。
組織にはさまざまな年齢層のスタッフがいますが、当然ながら私より年齢が上の部下の方もいらっしゃいます。
児童福祉の現場では、経験豊富なベテランスタッフの存在が非常に重要です。
しかし、正直に告白すると、最初から上手くいっていたわけではありません。むしろ、かなり苦労しました。
以前の会社で初めて管理職を任された際、私は年上部下との関係において大きく分けて2つの失敗パターンを繰り返していたのです。
当時の私は、管理職としてどう振る舞うべきかが分からず、極端に揺れ動いていました。
失敗パターン①:「偉くなった」勘違いで部下との壁を作ってしまった
会社から管理的な役割を与えられた当初、私のすけは完全に勘違いしていました。「自分が偉くなった」「管理職になったのだから、指示を出すのが仕事だ」と思い込んでいたのです。
今思えば恥ずかしい限りですが、年上の部下に対しても、立場を盾に高圧的な態度で指示を出すようなことをしてしまっていました。「私が責任者だから」という言葉を何度使ったことでしょう。
その結果、何が起きたか。
部下との間に見えない壁ができ、コミュニケーションが極端に減りました。報告・連絡・相談が上がってこなくなり、現場で何が起きているのか把握できない状況に陥ったのです。会議でも意見が出なくなり、空気が重くなっていきました。
「何かおかしい」と気づいたときには、すでにチーム全体の雰囲気が悪化していました。私の態度が、年上部下の方々のモチベーションを下げていたのです。
失敗パターン②:断れずに流され、判断軸がブレる日々
一方で、失敗パターン①に気づいた私は、今度は真逆の対応をしてしまいました。
年上部下の方々から「これはこうした方がいい」「昔からこのやり方でやってきた」と言われると、やりづらさを感じながらも断ることができず、そのまま要望を飲んでしまうようになったのです。
「年上だから経験豊富だし、きっと正しいんだろう」「反対して関係が悪くなるのは避けたい」という思いから、本来管理職として判断すべきことまで相手に委ねてしまっていました。
結果として何が起きたか。
組織としての方向性が定まらず、スタッフによって対応がバラバラになってしまったのです。Aさんの意見を取り入れたと思ったら、今度はBさんの真逆の意見も採用する。そんな一貫性のないマネジメントをしてしまっていました。
この状態では、チーム全体が混乱するのも当然です。部下からは「結局、のすけさんは何がしたいの?」という疑問の声も聞こえてくるようになりました。
管理職として一番やってはいけない「軸がブレる」状態に陥っていたのです。
転機となった気づき:富塚優さんの教えが私を変えた
高圧的になったり、逆に流されたり。両極端を行ったり来たりする日々の中で、私のすけは完全に行き詰まっていました。
「管理職に向いていないのかもしれない」
「年上部下をマネジメントするなんて、自分には無理なのかもしれない」
そんな弱気な気持ちが頭をよぎることも増えていました。
そんなある日、たまたまYouTubeで目にしたのが「ポケカルビジネスTV」の富塚優さんの動画でした。タイトルは年上部下との関わり方に関するものだったと記憶しています。
「また自己啓発系の綺麗事かな」と半信半疑で再生ボタンを押した私でしたが、富塚さんの言葉は違いました。現場のリアルな悩みを理解した上での、実践的なアドバイスだったのです。
その動画を見終わったとき、私の中で何かが変わりました。
まるで霧が晴れたように、自分が何を間違えていたのかが明確に見えてきたのです。
重要なのは「人としてのリスペクト」と「役割の明確化」
富塚さんの教えの中で特に印象的だったのは、人としてのリスペクトと、組織における役割の違いを明確に分けるという考え方でした。
私のすけはこれまで、「リスペクト」と「役割」をごちゃ混ぜにして考えていたのです。
高圧的だった時期は、「管理職という役割」だけを前面に出して、相手への「リスペクト」が欠けていました。
逆に流されていた時期は、「リスペクト」を優先しすぎて、「管理職としての役割」を放棄していたのです。
年上の部下を人生の先輩として心からリスペクトしながら、同時に組織における役割の違いははっきりと示す。この2つは矛盾しない。むしろ、両方があってこそ健全な関係が築けると今では感じています。
この気づきが、私のマネジメントを根本から変えることになりました。
のすけが実践した年上部下との付き合い方【3つのポイント】
富塚さんの教えをベースに、私のすけは年上部下との関わり方を根本から見直しました。
ここからは、実際に私が実践して効果があった具体的な方法を、リアルな体験を交えながらお伝えします。
正直、最初は勇気が必要でしたし、上手くいかないこともありました。
でも、続けることで確実に関係性が変わっていきました。
①人生の先輩としてリスペクトする姿勢をベースにする
まず大前提として、私のすけは年上の部下を「人生の先輩」としてリスペクトする姿勢を持つことを心がけました。
これは表面的な敬語を使うとか、形だけ丁寧にするという話ではありません。
心の底から、相手の人生経験や積み重ねてきた時間に敬意を払うということです。
例えば、私より10歳以上年上のスタッフの方は、私が学生だった頃から現場で子どもたちと向き合ってきた方々です。その経験の重みは、どんなに勉強しても簡単には得られるものではありません。
私はこのリスペクトの気持ちを、日々の小さなコミュニケーションの中で表現するように意識しました。
朝の挨拶、何気ない雑談、業務報告を受けるとき。
すべての場面で「この人の経験から学びたい」という姿勢を忘れないようにしたのです。
年齢や経験は、私のすけにはない価値です。
それを尊重する気持ちを常に持ち続けることが、信頼関係の土台になると確信しています。
②役割として任されている管理業務は明確に伝える
リスペクトをベースに持ちつつ、その上で組織における役割の違いははっきりと伝えることが重要です。
ここが私のすけにとって一番勇気が必要な部分でした。
「こんなことを言ったら、偉そうだと思われるんじゃないか」
「関係が悪くなったらどうしよう」という不安が頭をよぎりました。
しかし、曖昧なままにしておくことの方が、結果的にはお互いにとって良くないと気づきました。
私は意を決して、年上部下の方一人ひとりと1対1で面談の時間を設けました。
会議室に2人きりで座り、緊張しながらも、こう切り出しました。
「●●さん、今日は少しお時間をいただきたくて。私から直接お話ししたいことがあります。」
そして、こう続けました。
「私は●●さんを人生の先輩として本当にリスペクトしています。●●さんがこれまで積み重ねてこられた経験や知識は、私にはないものです。それは心から尊敬しています。」
まずはリスペクトの気持ちを明確に言葉にする。これが最初のステップでした。
そして、こう続けました。
「ただ、組織の中での役割として、私は会社から管理業務を任されています。ですから、チームの方針を決めたり、業務について指示をさせていただくことがあります。そこは立場上、指示を聞いていただきたいと思っています。」
この「リスペクト+役割の明確化」を最初に丁寧に伝えることで、お互いの立ち位置がクリアになりました。
意外だったのは、年上部下の方々の反応です。
「いや、そんなの当たり前でしょう」「のすけさんが責任者なんだから、指示してもらわないと困るよ」という反応が返ってきたのです。
むしろ、曖昧なままにしていたことの方が、相手にとってもやりづらかったのだと気づかされました。
役割を明確にすることは、相手への配慮でもあったのです。
③経験と知識を活かしてもらう場を作る
役割を明確にした後、私のすけはさらにこう付け加えました。
「ただし、もし気になることや疑問に思うことがあれば、いつでも言ってください。●●さんの知識と経験から意見をいただきたいんです。それは私にとって本当に貴重なものですから。」
この一言が、関係性を大きく変えました。
年上部下の方々は、豊富な経験と現場で培った知識を持っています。
しかし、年下の管理職の下では「意見を言ってもいいのか」「出しゃばりだと思われないか」と遠慮してしまう方も多いのです。
私が明確に「意見が欲しい」と伝えたことで、年上部下の方々も安心して発言できるようになりました。
実際、この方針を伝えてから、会議での発言が増えました。
例えば、新しい支援プログラムを導入しようとしたとき、ベテランスタッフの方から「似たようなことを10年前にやったことがあって、こういう課題があった」という貴重な情報をもらえました。
過去の失敗から学べることで、同じ轍を踏まずに済んだのです。
また、ある保護者対応で悩んでいたとき、年上のスタッフから「こういうケースは以前にもあって、こうアプローチしたら上手くいった」という具体的なアドバイスをもらったこともあります。
年上部下の方々の経験を引き出し、それを組織全体で活かす。そうすることで、相手も「自分の価値を認めてもらえている」「必要とされている」と感じてくれるのです。
これは単なるテクニックではなく、本当に私のすけ自身が助けられている実感があります。
情報収集と意思決定:のすけが大切にしている軸
年上部下の方々との関係が良好になってくると、自然と情報が集まるようになります。
私のすけも、定期的に年上スタッフの方々と雑談も含めて話を聞く時間を設けています。ランチを一緒にとったり、休憩時間に声をかけたり。フォーマルな面談だけでなく、カジュアルなコミュニケーションも大切にしています。
現場の生の声を聞く重要性
年上部下の方々は現場の最前線にいます。子どもたちの様子、保護者の反応、日々の小さな変化。そういった情報は、管理職の立場にいると見えにくくなりがちです。
だからこそ、私のすけは意識的に話を聞く機会を作っています。
「最近、現場で何か気になることはありますか?」
「●●さんの様子はどうですか?」
「この前の保護者面談、どんな感じでしたか?」
こういった質問を投げかけることで、組織の課題や改善点が見えてきます。
年上部下の方々からの情報は、判断材料として非常に有効なのです。
ただし、最終判断は自分が行う
ここで重要なのは、判断をするのはあくまでも自分という軸をぶらさないことです。
以前の私は、相談や意見を聞くと、そのまま全部を受け入れてしまっていました。しかし今は違います。
相談や意見は真摯に聞きます。貴重な情報として受け止めます。しかし、最終的な意思決定は管理職である自分が責任を持って行う。
この軸がブレると、組織全体の方向性が定まりません。また、何か問題が起きたとき「あの人が言ったから」と責任転嫁してしまうことにもなりかねません。
例えば、複数のスタッフから異なる意見が出たとき。
Aさんは「この支援方法がいい」と言い、Bさんは「別のアプローチの方がいい」と言う。どちらも経験に基づいた意見で、どちらも一理あります。
そんなとき、私のすけは両方の意見をしっかり聞いた上で、「では、今回はこういう理由でこちらの方法で進めます」と自分の判断を明確に示すようにしています。
そして大切なのは、その判断の理由も説明することです。
「なぜそう判断したのか」を伝えることで、たとえ自分の意見が採用されなかったスタッフも納得してくれます。
管理職としての責任を果たす。これが、年上部下との信頼関係を維持する上でも不可欠な要素だと、私のすけは学びました。
変化した組織の雰囲気:のすけが感じた3つの変化
この関わり方を実践してから、組織に明らかな変化が現れました。
私のすけ自身が日々実感している変化を、3つご紹介します。
変化①:報告・連絡・相談が増えた
以前は情報が上がってこなかったのに、今では積極的に報告や相談が来るようになりました。
年上部下の方から「のすけさん、ちょっといいですか」と声をかけられることが増え、現場の小さな変化や気づきを共有してもらえるようになったのです。
これにより、問題が大きくなる前に対処できるようになりました。
変化②:会議で活発な意見交換ができるようになった
以前は静まり返っていた会議が、今では活発な意見交換の場になっています。
年上のスタッフも遠慮なく意見を言ってくれるようになり、若手スタッフも刺激を受けて発言するようになりました。多様な視点から議論できることで、より良い判断ができるようになっています。
変化③:チーム全体のモチベーションが上がった
何より大きな変化は、チーム全体の雰囲気が明るくなったことです。
スタッフ同士の笑顔が増え、協力し合う姿勢が生まれました。年齢に関係なく、それぞれの強みを活かし合える関係性ができてきたのです。
結果として、子どもたちへの支援の質も向上しました。これが何より嬉しい変化です。
まとめ:のすけが学んだ年上部下との関係構築の本質
年上部下との付き合い方は、多くの管理職が悩むテーマです。私のすけ自身、かなり長い時間をかけて、失敗を繰り返しながらここまで辿り着きました。
今振り返ると、年上部下とのマネジメントで大切なのは、特別なテクニックやスキルではありませんでした。
それは**「リスペクト」「役割の明確化」「主体性」という3つのバランス**を保つことだったのです。
1. リスペクト:人生の先輩として敬意を持つ
相手の年齢、経験、積み重ねてきた時間に対して、心から敬意を払うこと。これは形だけではなく、本心からのリスペクトです。
2. 役割の明確化:組織における立場の違いをはっきり伝える
人としてのリスペクトと、組織における役割は別物です。管理職として方針を示し、指示を出すことは、立場上当然のことであり、むしろ責任でもあります。それを曖昧にせず、丁寧に伝えることが大切です。
3. 主体性:最終判断は自分が行うという軸を持つ
どんなに経験豊富な部下がいても、最終的な判断と責任は管理職である自分が負う。この軸をブレさせないことで、組織としての一貫性が保たれます。
あなたへのメッセージ:まず一歩を踏み出してみてください
もしあなたが今、年上部下との関係に悩んでいるなら、私のすけから一つアドバイスをさせてください。
それは、まずは1対1で丁寧に話す時間を作ってみることです。
「リスペクトしている」という気持ちを言葉にして伝えること。そして「役割として指示を出すこともあるが、あなたの意見も聞きたい」と明確に伝えること。
これがすべての始まりです。
私も最初は緊張しました。上手く言えるか不安でした。でも、勇気を出して一歩踏み出したことで、確実に関係性が変わりました。
完璧である必要はありません。誠実に向き合おうとする姿勢が、相手に伝わることが大切なのです。
年上部下とのマネジメントは、決して「どちらかが我慢する関係」ではありません。お互いの強みを活かし合い、組織としての成果を出しながら、人としても成長できる関係を築くことができるのです。
私のすけの体験が、同じ悩みを抱えるあなたの一助になれば幸いです。
一緒に、より良いチームを作っていきましょう。
【関連情報】
参考にした動画:ポケカルビジネスTV(富塚優さん)
※YouTubeで「年上部下 富塚優」などで検索すると関連動画が見つかります

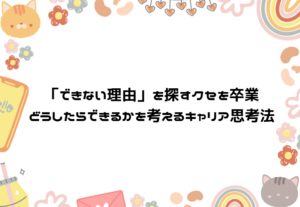
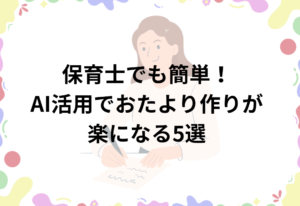
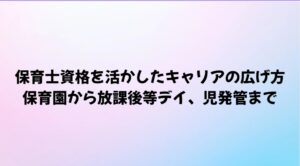
コメント