つい「できません」と答えていませんか?
「この案件、来週までにできますか?」
「新しいプロジェクト、担当してもらえる?」
「この資料、明日の朝までに準備できる?」
こんな依頼を受けたとき、あなたの頭の中で最初に浮かぶのは何でしょうか?
「時間がないから無理」
「経験がないからできない」
「リソースが足りないから不可能」
もしこんな風に「できない理由」が真っ先に思い浮かんでしまうなら、それはもったいない思考のクセかもしれません。

こんにちは、のすけです。
雑記ブログを運営している30代です。
実は私も以前は「できない理由探し」の達人でした。新しい挑戦の前に立つと、まず頭に浮かぶのは「なぜそれが不可能なのか」の理由ばかり。
でも、尊敬する先輩から教わった一つの考え方が、私のキャリアを大きく変えることになりました。
今日は、その体験談と、科学的な根拠も交えながら「できない理由」から「できる方法」へ思考を転換する具体的な方法をお話しします。
人生を変えた先輩からの一言
「できないと言う前に、どうすればできるかを考えてみて」
転職して2年目、私は新しいプロジェクトのリーダーを任されそうになっていました。でも、正直自信がありませんでした。



のすけ:「すみません、経験もないし、人をまとめるのも得意じゃないので…できないと思います」
そのとき、尊敬している先輩がこう言いました。
先輩:「のすけ君、”できない”と言う前に、”どうすればできるか”を考えてみない?その思考の違いが、キャリアの分かれ道になるよ」
最初は「きれいごとだな」と思いました。でも先輩は続けます。
先輩:「例えば、経験がないなら誰から学べばいい?人をまとめるのが苦手なら、どんなスキルを身につければいい?まずはそこから考えてみよう」
思考の転換が始まった瞬間
その一言で、私の頭の中にスイッチが入りました。
「経験がない」→「経験豊富な人から学ぼう」
「人をまとめるのが苦手」→「リーダーシップの本を読んで、研修に参加しよう」
「時間がない」→「タスクを整理して、効率的なスケジュールを組もう」
不思議なことに、「できない理由」を「解決すべき課題」に置き換えただけで、頭の中が整理され、やるべきことが明確に見えてきたのです。
結果として、私のキャリアにおける大きなターニングポイントになりました。



のすけ:「今思えば、あの一言がなければ今の自分はなかったかもしれません」
補足:以前の私は「できない理由探し」のプロでした
実は、この先輩との出会いまで、私は典型的な「できない理由探し」タイプでした。
過去の思考パターン
新しい仕事を依頼されたとき:
- 「この仕組みがないからできない」
- 「前例がないから危険」
- 「時間がないから無理」
- 「知識が足りないから不可能」
転職を考えたとき:
- 「経験年数が足りない」
- 「スキルが不十分」
- 「今の会社を辞められない理由がある」
振り返ってみると、挑戦する前に脳が「できない」と認識して、行動にブレーキをかけていました。
変化のきっかけ
先輩の教えを受けてから、意識的に思考パターンを変える練習を始めました。
Before(できない理由を探す) → After(できる方法を考える)
この単純な転換が、驚くほど大きな変化をもたらしました。
- 新しい挑戦に積極的になった
- 問題解決能力が向上した
- 周囲からの信頼度が上がった
- キャリアの選択肢が広がった



のすけ:「脳の使い方を変えただけで、こんなにも現実が変わるとは思いませんでした」
「できない」思考が脳に与える悪影響
科学的根拠①:セルフフルフィリングプロフェシー(自己成就予言)
心理学の研究で明らかになっているのが、セルフフルフィリングプロフェシー(自己成就予言)という現象です。
これは「自分が信じたことが現実になりやすい」という理論で、1968年の教育心理学者ロバート・ローゼンタールの実験で実証されました。
「できない」と思考すると:
- 脳がそれを前提に行動パターンを決める
- 挑戦する前に諦める行動を取る
- 結果として本当に「できない」結果になる
- さらに「やっぱりできなかった」と信念が強化される
科学的根拠②:学習性無力感
アメリカの心理学者マーティン・セリグマンが提唱した学習性無力感も重要な概念です。
繰り返し「できない」「無理」と思うことで:
- 挑戦意欲が低下する
- 新しい解決策を探そうとしなくなる
- 実際にはコントロール可能な状況でも諦めてしまう
- 長期的にうつ症状につながる可能性もある
脳科学的視点:RAS(網様体賦活系)
脳にはRAS(網様体賦活系)という情報フィルター機能があります。
「できない」にフォーカスすると:
- 脳が「できない理由」ばかりを情報収集する
- 「できる可能性」に関する情報を見落とす
- 結果として解決策が見えなくなる
「どうすればできるか」にフォーカスすると:
- 脳が「解決策」や「可能性」を探し始める
- 今まで見えなかった選択肢が見えてくる
- 創造的なアイデアが生まれやすくなる



のすけ:「脳は自分が注目している情報を優先的に集める性質があるんですね」
「できない理由」を「解決の方向性」に変換する実践フレーム
ここからは具体的な変換方法を解説します。よくある「できない理由」と、それを「解決策」に転換する思考パターンをご紹介しますね。
パターン①:「やり方がわからない」
❌ できない理由思考 「この作業、やったことがないからできません」
✅ 解決策思考 「やり方を学べば解決できる問題ですね」
具体的アクション:
- Google検索で情報収集
- 書籍・動画で学習
- 経験者に相談・教えを請う
- 研修やセミナーに参加
- 試行錯誤しながら実践
パターン②:「時間がない」
❌ できない理由思考 「忙しすぎて時間がないので無理です」
✅ 解決策思考 「時間を作る方法を考えれば解決できますね」
具体的アクション:
- 現在のタスクを整理・優先順位付け
- 不要な作業の削減
- 効率化ツールの導入
- 他者への委託・協力依頼
- 時間の使い方の見直し
パターン③:「やる気が出ない」
❌ できない理由思考 「モチベーションが上がらないからできません」
✅ 解決策思考 「やる気を出すために目的を明確化すれば解決できますね」
具体的アクション:
- なぜその仕事が重要かを再確認
- 達成後のメリットを具体化
- 小さな目標に分解して達成感を味わう
- 協力者と一緒に取り組む
- 報酬や楽しみを設定
パターン④:「仕組みがない」
❌ できない理由思考 「システムが整っていないからできません」
✅ 解決策思考 「仕組みを作れば解決できる問題ですね」
具体的アクション:
- 必要なツールを調査・導入
- ルールやプロセスを設計
- チームメンバーと仕組みを共有
- 試行錯誤で改善を重ねる
- 上司に相談して環境整備を依頼
パターン⑤:「継続できない」
❌ できない理由思考 「どうせ続かないからやっても無意味です」
✅ 解決策思考 「続けられる仕組みを作れば解決できますね」
具体的アクション:
- 習慣化のためのトリガーを設定
- 周囲に宣言して外的圧力を作る
- 進捗を可視化するツールを使用
- 小さな成功体験を積み重ねる
- 継続できない原因を分析して改善



のすけ:「『できない理由』は全て『解決すべき課題』に変換できるんです」
読者が実践できるチェックリスト
「できない」と思ったときに使える5つの問いをご紹介します。スマホのメモ帳に保存して、いつでも使えるようにしておくと便利ですよ。
🔍 思考転換チェックリスト
❓ 問い1:「本当にできないのか?」
- 物理的・法的に不可能なのか?
- それとも難しいだけなのか?
- 過去に成功例はないか?
❓ 問い2:「何が障害になっているのか?」
- 知識不足?経験不足?
- 時間不足?リソース不足?
- 仕組みの問題?環境の問題?
❓ 問い3:「その障害は解決可能か?」
- 学習で解決できる?
- 時間をかければ解決できる?
- 協力者がいれば解決できる?
❓ 問い4:「誰に相談すれば解決のヒントが得られるか?」
- 経験豊富な先輩
- その分野の専門家
- 過去に同じ課題を解決した人
❓ 問い5:「最初の一歩は何から始められるか?」
- 今日中にできることは?
- 5分でできることは?
- 情報収集から始められることは?
💡 実践のコツ
毎日の習慣にする:
- 朝の通勤時間に昨日の「できない理由」を振り返る
- 「どうすればできるか」に置き換えて考える
- 夜寝る前に今日の思考転換を記録する
周囲の人と共有する:
- 家族や友人に「できない理由探しをやめる宣言」をする
- 職場のチームメンバーと解決策思考を共有する
- 定期的に進捗を報告し合う



のすけ:「最初は意識的にやる必要がありますが、慣れてくると自然に考えられるようになります」
実際に変化を実感した具体例
ケース①:プレゼンテーションスキル
Before:「人前で話すの苦手だからできません」 After:「どうすれば上手く話せるようになるか考えよう」
実行したこと:
- トーストマスターズクラブに参加
- YouTubeでプレゼン技術を学習
- 鏡の前で練習
- 小さな勉強会から場数を踏む
結果: 部署内プレゼン大会で優勝、社外セミナーで講師を務めるまでに成長
ケース②:英語での会議参加
Before:「英語できないから国際会議は無理です」 After:「英語力を向上させる方法を考えよう」
実行したこと:
- オンライン英会話を毎日30分
- 業界の英語表現を重点的に学習
- 外国人の同僚とランチ英会話
- 英語の会議に最初は聞くだけ参加
結果: 半年後には英語での会議で積極的に発言、海外プロジェクトにアサインされた
ケース③:副業ブログ運営
Before:「文章書くの下手だからブログなんて無理」 After:「どうすれば読まれる文章が書けるようになるか」
実行したこと:
- ライティング本を10冊読破
- 人気ブロガーの記事を分析
- 毎日500文字の日記から開始
- ライティング講座を受講
結果: 月間10万PVのブログに成長、副業収入も安定的に確保



のすけ:「『できない理由』を『できる方法』に変える習慣が、確実にキャリアを変えていきました」
キャリアにおける思考転換の威力
上司・同僚からの評価が変わる
「できない理由」を言う人の印象:
- 消極的
- 責任感が薄い
- 成長意欲が低い
- チームワークに欠ける
「どうすればできるか」を考える人の印象:
- 積極的で前向き
- 問題解決能力が高い
- 学習意欲旺盛
- チームに貢献的
新しい機会が舞い込みやすくなる
解決策思考の人には:
- 重要なプロジェクトが任される
- 昇進の機会が増える
- 研修や学習機会が提供される
- 転職時にも高く評価される
セルフイメージが向上する
心理的な変化:
- 自己効力感(自分ならできるという感覚)が高まる
- 挑戦することが楽しくなる
- ストレス耐性が向上する
- ポジティブな思考が習慣になる
まとめ:思考の習慣がキャリアを決める
「できない理由」を探すのは実は簡単です。どんなことにでも、探せば障害や問題は見つかります。
でも「どうしたらできるか」を考える習慣こそが、キャリアを大きく変える分かれ道になるのです。
先輩の教えが今も私を支えています
あの日、尊敬する先輩から教わった「できないと言う前に、どうすればできるかを考えてみて」という一言。
その教えのおかげで:
- 新しい挑戦を恐れなくなりました
- 困難な状況でも解決策を見つけられるようになりました
- 周囲からの信頼を得られるようになりました
- そして、このブログを通じて多くの人とつながることができています
変化は今からでも可能です
もし今「できない理由探し」がクセになってしまっていても大丈夫です。私も最初はそうでした。
大切なのは:
- 自分の思考パターンを自覚すること
- 意識的に「どうすればできるか」を考えること
- 小さな成功体験を積み重ねること
- 継続して習慣化すること
読者の皆さんへのエール
今日からぜひ試してみてください。
次に「できない」と思った瞬間、立ち止まって問いかけてみてください:
「どうすればできるだろうか?」
その一つの問いが、あなたのキャリアの新しい扉を開くかもしれません。



のすけ:「思考を変えれば行動が変わり、行動が変われば結果が変わります。一緒に『できる方法を考える人』になっていきましょう」
この記事が少しでも参考になったら、ぜひシェアしてください。キャリア形成や働き方に関する他の記事もありますので、よろしければご覧ください。あなたの思考転換体験があれば、コメント欄で教えてくださいね!
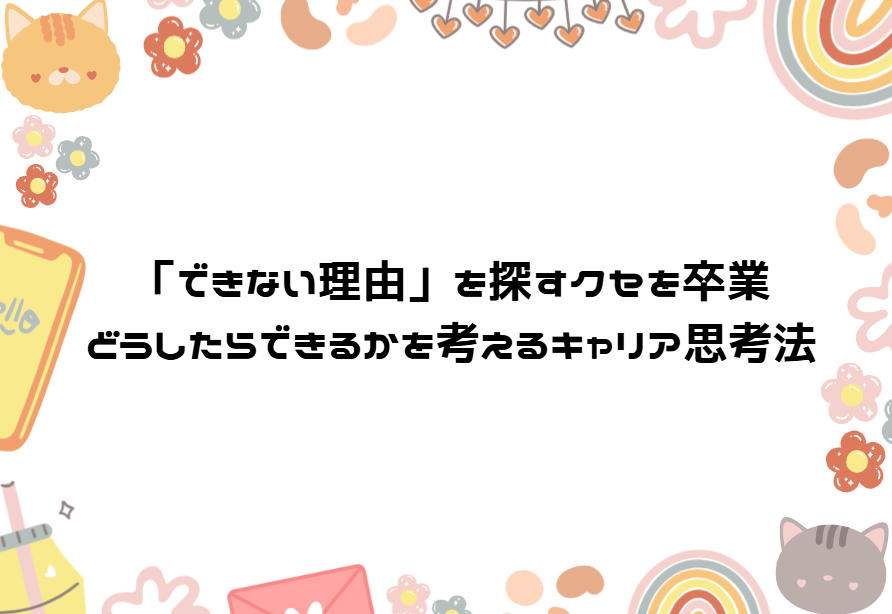

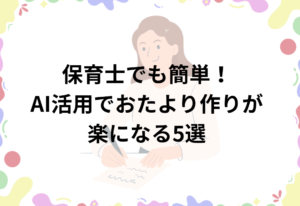
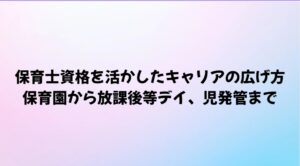
コメント