朝と夜の習慣ルーティン10選|忙しい30代でも”1秒だけ”で続けられる心理学
習慣を続けるのって、本当に難しいですよね。
こんにちは、のすけです。
30代福祉系会社で支援員をしています。
実は僕、中学・高校時代から「今度こそ習慣を身につけるぞ!」と何度も意気込んでは、結局3日坊主で終わることを繰り返してきました。
日記、筋トレ、読書、英語学習…数えきれないほどの「今度こそは」がありました。
でも、ある心理学の考え方に出会ってから、僕の習慣に対する考え方が180度変わったんです。それが「1秒・1回でもやる」という考え方でした。
完璧を目指さず、とにかく小さく始める。
この考え方を取り入れてから、朝と夜のルーティンが自然と身につき、今では毎日続けることができています。
この記事では、僕が実際に続けている朝・夜の習慣と、科学的・心理学的な根拠に基づいた「続けるコツ」をお伝えします。
読み終わる頃には、明日からでも始められる具体的な習慣と、挫折しても立ち直れるリカバリー方法がわかるはずです。
1. 習慣は”1秒だけ”から始める(心理学的根拠つき)
僕が習慣を続けられるようになった最大のポイントは、「完璧にやろうとしない」ことでした。
以前の僕は「筋トレするなら30分はやらないと意味がない」「読書は最低でも1時間は読まないと」と考えていました。でも、これが大きな間違いだったんです。
スタンフォード大学のBJフォッグ博士が提唱する「Tiny Habits理論」によると、
新しい習慣を身につけるには、できるだけ小さく始めることが重要だとされています。
フォッグ博士は「歯を磨いた後に、フロスを1本の歯にだけ使う」といった極小の行動から始めることを推奨しています。
また、心理学者のロバート・ザイアンスが発見した「作業興奮」という現象も重要です。
これは、実際に行動を始めると脳が活性化し、「やる気」が後から付いてくるという現象です。
つまり、「やる気があるから行動する」のではなく、「行動するからやる気が出る」のです。
僕の場合、筋トレなら「腕立て伏せを1回だけ」、読書なら「本を開いて1行だけ読む」から始めました。
実際にやってみると、1回だけのつもりが「せっかくだからもう少し」となることが多いんです。でも、もし1回だけで終わっても、それで十分。「今日もやった」という成功体験が積み重なっていきます。
実際の取り入れ方:
- 所要時間:文字通り1秒〜10秒
- 始め方:既存の習慣(歯磨き、コーヒーを飲むなど)の後に行う
- 心構え:「これだけでも十分」と自分を認める
2. 朝のルーティン(ウォーキング・ストレッチ・英単語・ブログ)
朝の時間は、一日の始まりとして特に大切にしています。僕の朝のルーティンは以下の通りです。
① ウォーキング(5〜15分)
起床後、すぐに外に出ます。最初は「玄関を出て、近所を1周するだけ」から始めました。今では平均10分程度歩いていますが、忙しい日や体調が優れない日は「玄関を出て深呼吸3回」だけでもOKとしています。
朝の日光を浴びることで、セロトニンの分泌が促進され、体内時計がリセットされます。
これは睡眠研究で有名な明治薬科大学の駒田陽子教授らの研究でも実証されています。
実際の実感: 朝の散歩を始めてから、夜の寝つきが格段に良くなりました。また、歩きながら今日やることを整理する時間にもなっています。
所要時間: 5〜15分(最短は玄関出て深呼吸3回=1分)
② ストレッチ(2〜5分)
ウォーキングから帰宅後、簡単なストレッチを行います。
最初は「両手を上に伸ばすだけ」から始めました。
現在は肩回し、首のストレッチ、前屈など基本的な動きを2〜5分程度行っていたり。
「朝・ヨガ」「朝・ストレッチ」などとYouTubeで検索して、動画を見ながら10分ほどストレッチをしています。
僕がよく見ているYouTuberさんをお二人下記に紹介します!
実際の実感: デスクワークが多い僕にとって、朝のストレッチは一日の体の調子を整える大切な時間になっています。肩こりも軽減されました。
③ 英単語学習(1〜3分)
スマートフォンの単語アプリを使って、英単語を覚えています。最初は「アプリを開いて1単語だけ見る」から始めました。今では毎朝5〜10単語程度チェックしています。
心理学者ヘルマン・エビングハウスの「忘却曲線」理論によると、記憶は時間とともに急激に減少しますが、定期的な復習により記憶の定着率が向上します。朝の短時間学習は、この理論を活用した効率的な記憶法です。
実際の実感: 短時間でも毎日続けることで、語彙力の向上を実感しています。朝の頭がクリアな時間に学習することで、記憶に残りやすい気がします。
所要時間: 1〜3分(最短はアプリを開いて1単語見るだけ=10秒)
④ ブログ執筆(5〜30分)
最後に、簡単な日記や気づきをブログに書きます。最初は「今日の天気を1行書くだけ」から始めました。現在では、前日の振り返りや今日の目標などを5〜30分程度で書いています。
実際の実感: 文章を書くことで思考が整理され、一日をより意識的に過ごせるようになりました。また、後で読み返すと自分の成長や変化に気づけて面白いです。
所要時間: 5〜30分(最短は天気を1行書くだけ=30秒)
挫折エピソード: 実は朝のルーティン、最初は全然続きませんでした。特に冬の朝は寒くて、ウォーキングをサボることが多かったんです。でも「玄関まで行って外の空気を吸うだけでもOK」というルールに変更してから、続けやすくなりました。
3. 夜のルーティン(筋トレ・日記・読書・目のケア・英語音読)
夜の時間は、一日の疲れをリセットし、明日への準備をする大切な時間です。僕の夜のルーティンは以下の通りです。
① 筋トレ(3〜15分)
夕食後、簡単な筋トレを行います。最初は「腕立て伏せ1回」から始めました。
現在では腕立て伏せ、スクワット、プランクなど基本的な種目を3〜15分程度行っています。
前述の「作業興奮」の効果で、1回だけのつもりが「もう少しやろうかな」となることが多いです。
でも、体調が悪い日や忙しい日は、本当に1回だけでも十分としています。
実際の実感: 少しずつですが、体力がついてきているのを実感しています。何より「今日も筋トレした」という達成感が、一日を良い気分で終えることにつながっています。
所要時間: 3〜15分(最短は腕立て伏せ1回=10秒)
② 日記(2〜10分)
一日の出来事や気づきを日記に書きます。最初は「今日良かったことを1つだけ書く」から始めました。現在では、良かったこと、反省点、明日の目標などを2〜10分程度で書いています。
ポジティブ心理学の創始者マーティン・セリグマンの研究によると、感謝の気持ちや良いことを書き出す習慣は、幸福感の向上と抑うつ症状の軽減に効果があることが実証されています。
実際の実感: 日記を書くことで、一日の中の小さな良いことに気づけるようになりました。また、悩みごとも文字にすることで客観視でき、解決策が見えやすくなります。
所要時間: 2〜10分(最短は良かったこと1つ書く=30秒)
③ 読書(5〜20分)
ベッドに入る前に、本を読みます。最初は「本を開いて1ページ読む」から始めました。現在では5〜20分程度読んでいます。
実際の実感: 読書を習慣化することで、知識が積み重なっていくのを実感しています。また、読書は良い睡眠導入にもなっています。
所要時間: 5〜20分(最短は1ページ読む=1分)
④ 目のケア(1〜3分)
デスクワークによる目の疲れを軽減するため、目を温めたり、目の体操を行います。最初は「目をぎゅっと閉じて開くを1回」から始めました。
実際の実感: 目のケアを始めてから、眼精疲労による頭痛が減りました。また、リラックス効果もあり、睡眠の質が向上したと感じています。
所要時間: 1〜3分(最短は目を閉じて開く1回=5秒)
⑤ 英語音読(2〜10分)
英語の教材を音読します。最初は「英語の文章を1文だけ音読」から始めました。現在では2〜10分程度、様々な教材を音読しています。
実際の実感: 音読することで、英語のリズムや発音が身についてきました。また、朝の英単語学習との相乗効果で、英語力の向上を実感しています。
所要時間: 2〜10分(最短は1文音読=10秒)
挫折エピソード: 夜のルーティンで一番挫折しやすいのが筋トレでした。仕事で疲れた日は「今日くらいサボってもいいか」と思ってしまうんです。そんな時は、ベッドの上で「仰向けになって両足を上げるだけ」でもOKというルールにしています。形は違っても「筋肉を動かした」という事実が大切だと考えています。
4. 習慣が続かないときのリカバリー法(心理学的解説)
どんなに小さく始めても、習慣が途切れることはあります。大切なのは、完璧を目指さず、リカバリーする方法を知っておくことです。
リカバリー法① If-Thenプランニング
心理学者ピーター・ゴルヴィッツァーが提唱する「If-Thenプランニング」は、事前に「もし〜なら、〜する」という計画を立てておく手法です。
僕の場合:
- 「もし朝寝坊したら、通勤電車で英単語1つだけ覚える」
- 「もし筋トレをサボったら、歯磨きの間だけスクワットする」
- 「もし日記を忘れたら、翌朝コーヒーを飲みながら前日のことを1行書く」
実際の効果: 予備プランがあることで、「今日はダメだった」という罪悪感が軽減され、すぐに習慣軌道に戻れるようになりました。
リカバリー法② ナッジ理論の活用
行動経済学者のリチャード・セイラーとキャス・サンスタインが提唱する「ナッジ理論」は、人の行動を強制ではなく、環境を整えることで自然に促す考え方です。
僕の工夫:
- 筋トレ用のマットを常に敷きっぱなしにする(視覚的なリマインダー)
- 英単語アプリをスマートフォンのホーム画面に配置する
- 日記帳とペンを常に枕元に置く
- 読書用の本を複数の場所に配置する(リビング、寝室、カバンの中)
実際の効果: 環境を整えることで、習慣を思い出すきっかけが増え、自然と行動に移せるようになりました。
リカバリー法③ 段階的復帰法
心理学の「段階的暴露法」を応用し、習慣が途切れた後は段階的に元のレベルに戻していきます。
例えば、1週間筋トレをサボった場合:
- 1日目:腕立て伏せ1回だけ
- 2日目:腕立て伏せ3回
- 3日目:腕立て伏せ5回と軽いストレッチ
- 4日目以降:通常のメニューに戻る
実際の効果: いきなり元の強度に戻そうとして再び挫折することがなくなりました。階段を上るように、少しずつ習慣の強度を上げていくことで、無理なく復帰できています。
僕の最大の挫折エピソード: 昨年の12月、年末の忙しさで全ての習慣が1週間途切れてしまいました。「もうダメだ、また続かなかった」と思いましたが、「1月1日から、また1秒・1回から始めよう」と決めました。実際に腕立て伏せ1回、英単語1個から再スタートし、現在まで続いています。
5. 続けるための工夫とまとめ
習慣を続けるために、僕が実践している具体的な工夫をお伝えします。
工夫① 記録は「やった・やらない」だけ
詳細な記録は続きません。僕はカレンダーに「○」か「×」だけをつけています。「○」の連続を見ると達成感があり、「×」があっても「明日は○にしよう」と前向きになれます。
工夫② 完璧主義を捨てる
「毎日完璧にやらなければ意味がない」という考えを捨てました。週7日のうち5日できれば上出来、3日できれば合格点としています。
工夫③ 習慣をセットで行う
朝のルーティンは「起床→着替え→ウォーキング→ストレッチ→英単語→ブログ」と一連の流れにしています。一つの行動が次の行動のトリガーになり、自然と全てが続きます。
工夫④ 環境を味方につける
物理的な環境を習慣に有利になるよう整えています。ストレッチマットを常に敷いておく、本を手の届く場所に置く、スマートフォンの通知で習慣をリマインドするなどです。
工夫⑤ 小さな成功を祝う
「今日も腕立て伏せ1回できた」「3日連続で日記を書けた」など、小さな成功も自分を褒めることにしています。これが次の行動への動機になります。
まとめ
習慣作りで最も大切なのは、完璧を目指すのではなく、小さく始めて続けることです。
僕が学んだ重要なポイントは以下の通りです:
心理学的に効果的なアプローチ:
- Tiny Habits理論:できるだけ小さく始める
- 作業興奮:行動することでやる気が後からついてくる
- If-Thenプランニング:挫折した時の対処法を事前に決める
- ナッジ理論:環境を整えて自然に行動を促す
実践的な工夫:
- 「1秒・1回でもやる」という最低限のハードル設定
- 既存の習慣の後に新しい習慣をつける
- 記録はシンプルに「○×」だけ
- 挫折しても段階的復帰法で無理なく再開
習慣は一日にしてならず、でも毎日の小さな積み重ねが大きな変化を生み出します。
さあ、読んでくださったあなたも今日から始めてみませんか?まずは今夜、ベッドに入る前に腕立て伏せを1回だけやってみましょう。それだけで十分です。明日の朝、「昨日腕立て伏せをした」という小さな成功体験から、新しい習慣の第一歩がスタートします。
習慣作りの旅は、完璧である必要はありません。大切なのは始めること、そして続けることです。一緒に小さな習慣から、大きな変化を作っていきましょう!
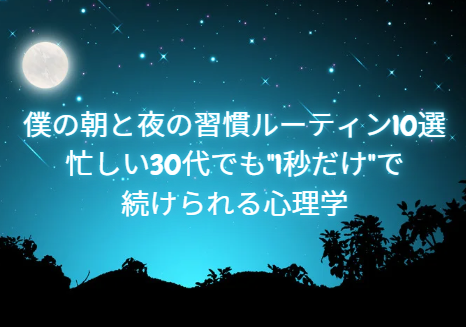
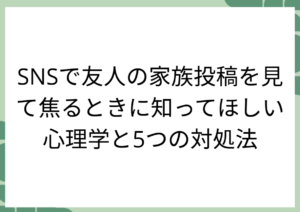
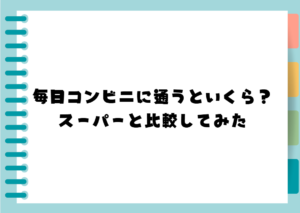

コメント