「何度言っても同じこと繰り返す」のは当たり前だった
「さっきも注意したばかりなのに、また叩いてる…」
兄弟げんかで手が出るわが子を見て、こんなふうに感じたことはありませんか?
「うちの子、学習能力がないのかな」 「私の育て方が間違ってる?」 「発達に何か問題があるのかも…」
でも実は、「何度言っても手が出る」のは、子どもの脳の発達段階から見れば、極めて自然なことなんです。
この記事では、教育論や精神論ではなく、脳科学の視点から「なぜ子どもは手が出やすいのか」「いつ頃から変わってくるのか」を解説します。
理屈がわかると、目の前の行動が「困った問題」から「発達の通過点」に見えてきます。
子どもの脳は「工事中」―前頭前野の発達タイムライン
まず知っておきたいのは、人間の脳は、後ろから前に向かって発達するということ。
脳の後ろ側(視覚や聴覚を処理する部分)は比較的早く完成しますが、前側、特に前頭前野と呼ばれる部分の発達はとてもゆっくりです。
前頭前野が担っている役割
- 衝動を抑える(ブレーキをかける)
- 感情をコントロールする
- 複数の情報を統合して判断する
- 「今やりたいこと」より「やるべきこと」を優先する
- 相手の気持ちを想像する
まさに、「大人っぽい行動」を支える司令塔です。
年齢別の発達段階
2〜3歳:前頭前野はまだほぼ未発達
- 「待つ」「我慢する」がほとんどできない
- 感情と行動が直結している
- 「叩いちゃダメ」を覚えていても、カッとなると忘れる
4〜5歳:前頭前野が動き始めるが、まだ不安定
- 調子がいいときは我慢できるが、疲れていると無理
- 「次はこうしよう」が理解できるようになってくる
- でも実行できるかは別問題
6〜8歳:前頭前野が発達してくるが、まだ完成には程遠い
- 「叩いちゃダメ」は理解しているが、瞬間的には抑えられない
- 後から「やっちゃった…」と後悔できるようになる
- 成功体験を積むことで、少しずつコントロールできる時間が延びる
思春期〜成人:ようやく完成に近づく
- 前頭前野が完全に発達するのは、なんと20代半ば
- 10代でも、まだ衝動的な行動は起こりやすい
つまり、小学校低学年で「すぐ手が出る」のは、脳の発達段階としては当然なんです。
「アクセル」と「ブレーキ」のバランス
子どもの行動を理解するには、「アクセル」と「ブレーキ」の関係を知るとわかりやすくなります。
アクセル:扁桃体(感情を生み出す部分)
- 生まれたときからフル稼働
- 「イヤだ!」「ムカつく!」といった感情を瞬時に生み出す
- 特に幼児期は過敏で、些細なことでも大きく反応する
ブレーキ:前頭前野(衝動を抑える部分)
- 発達に時間がかかる
- 使えば使うほど強くなるが、疲れると効きが悪くなる
- ストレスや空腹、睡眠不足でも機能が低下する
子どもは、「アクセル全開、ブレーキなし」の車のような状態で日常を過ごしているわけです。
そう考えると、「手が出ちゃう」のも無理はないですよね。
なぜ「言葉より先に手が出る」のか―脳の処理スピードの違い
もうひとつ重要なのが、感情と言葉の処理スピードの違いです。
感情の処理:0.1秒
扁桃体は、危険や不快を感じると、0.1秒という超高速で反応します。
これは生存本能に関わる部分なので、意識する前に身体が動きます。
言葉の処理:数秒〜数十秒
一方、言葉を使うには、以下のプロセスが必要です。
- 感情に気づく
- その感情を言語化する
- 相手に伝わる文章を組み立てる
- 口に出す
このプロセスには、数秒から数十秒かかります。
つまり、感情が生まれてから言葉にするまでの間に、圧倒的なタイムラグがあるんです。
結果:身体が先に動く
「イヤだ!」と感じた瞬間(0.1秒後)には、もう手が出ている。
言葉を組み立て終わる頃(数秒後)には、もう叩いた後。
子どもが「どうして叩いたの?」と聞かれても答えられないのは、自分でもなぜ叩いたのか、言語化できていないからなんです。
「疲れてるとき」「空腹時」「夕方」に手が出やすい理由
「なんか最近、夕方になると兄弟げんかが増える気がする…」
そんなこと、ありませんか?
これも、脳科学的に説明がつきます。
前頭前野は「エネルギー消費が激しい」
ブレーキ役の前頭前野は、脳の中でも特にエネルギーを使う部分。
だから、
- 疲れているとき:エネルギー不足でブレーキが効かない
- 空腹時:血糖値が下がり、脳の機能が低下
- 夕方:一日の疲労が蓄積し、前頭前野の機能が落ちる
- 睡眠不足:脳の回復が不十分で、そもそもブレーキが弱い
つまり、**「何度言ってもわからない」のではなく、「身体的条件が整っていない」**だけなんです。
実践的な対策
これを理解すると、対策も見えてきます。
- 夕方は兄弟を別々の部屋で遊ばせる
- おやつの時間を見直す(夕方の空腹を防ぐ)
- 睡眠時間を確保する(夜は早めに寝かせる)
- 疲れているサインが見えたら、先回りして距離を取らせる
「その場で叱る」より、「手が出にくい環境を作る」方が、ずっと効果的です。
「できた!」の瞬間に何が起きているのか―脳の回路を強化するメカニズム
「さっき、叩かずに『イヤだ』って言えたね!」
こんなふうに褒められたとき、子どもの脳では何が起きているのでしょうか。
脳は「使った回路」が強化される
脳には、**「使った神経回路ほど太く、強くなる」**という性質があります。
- 手を出す→「手を出す回路」が強化される
- 言葉で言う→「言葉で言う回路」が強化される
つまり、成功体験を積むことで、新しい行動パターンが脳に定着していくんです。
「褒める」が回路を加速させる
さらに、褒められると脳内でドーパミン(快感物質)が分泌されます。
ドーパミンが出ると、
- その行動が「気持ちいいこと」として記憶される
- 次も同じ行動をしたくなる
- 学習スピードが上がる
だから、「叩かなかった瞬間」「言葉で言えた瞬間」を見逃さず、その場で具体的に褒めることが、脳科学的にも非常に効果的なんです。
「何度も繰り返す」のは脳が学習している証拠
「もう10回も同じこと言ってるのに…」
そう感じるとき、多くの親は「うちの子、覚えられないのかな」と不安になります。
でも、繰り返しこそが学習の本質です。
脳は「繰り返し」でしか変わらない
新しい神経回路が定着するには、数百回〜数千回の繰り返しが必要だと言われています。
- 自転車に乗れるようになるまで、何度も転ぶ
- 九九を覚えるまで、何度も唱える
- 字を書けるようになるまで、何度も練習する
「手を出さずに言葉で言う」というのも、同じこと。
何度も失敗しながら、少しずつ脳に新しい回路を作っているんです。
「できない日」があっても当然
さらに、脳の発達は一直線ではありません。
- 昨日はできたのに、今日はできない
- 午前中はできたのに、夕方はできない
これは「後退」ではなく、脳が新しい回路を試行錯誤している過程です。
3歩進んで2歩下がる、それを繰り返しながら、少しずつ前に進んでいきます。
「いつ頃から変わる?」―発達の目安
「じゃあ、うちの子はいつになったら手が出なくなるの?」
これは親として、いちばん知りたいところですよね。
一般的な発達の目安
3〜4歳頃
- まだ衝動コントロールはほぼ無理
- でも「ダメなことをした」という認識は芽生え始める
5〜6歳頃
- 調子がいいときは、数秒我慢できるようになる
- 「次はこうしよう」と計画を立てられるようになる
7〜8歳頃
- 手を出す前に「やばい」と気づける瞬間が増える
- 失敗したときに、後から理由を説明できるようになる
9〜10歳頃
- 多くの場面で、衝動的に手を出すことが減る
- でもストレスが高いときは、まだ出ることもある
ただし、これには大きな個人差があります。
発達の早い子もいれば、ゆっくりな子もいる。それは知能や性格の問題ではなく、脳の発達ペースの個人差です。
親の関わり方が「ブレーキの発達」を左右する
脳の発達には個人差がありますが、環境によって発達スピードが変わることもわかっています。
ブレーキの発達を促す関わり
- 感情を言語化してあげる
- 「悔しかったんだね」「イヤだったね」
- 脳が感情と言葉を結びつける
- 成功体験を積ませる
- できた瞬間を見逃さず褒める
- 新しい回路が強化される
- 代わりの行動を教える
- 「『イヤだ』って言ってみる?」
- 行動の選択肢が増える
- 失敗を責めない
- 「また叩いちゃったね。悔しいね」
- 安心して挑戦できる環境を作る
ブレーキの発達を妨げる関わり
- 強く叱りすぎる
- 恐怖で行動を抑えようとすると、前頭前野ではなく恐怖回路が働く
- 自発的な抑制力が育ちにくい
- 「なんでできないの!」と責める
- 自己肯定感が下がると、挑戦する意欲が失われる
- 新しい回路を作ろうとする力が弱まる
- 変化を認めない
- 「全然変わってない」と言われると、子どもは諦める
- 小さな進歩を見逃さないことが大切
まとめ:「問題行動」ではなく「発達の通過点」として見る
すぐ手が出てしまう子は、決して「困った子」ではありません。
ただ、脳の発達がまだ途中なだけ。
- 前頭前野の発達には時間がかかる
- 感情は0.1秒、言葉は数秒かかる
- 疲れや空腹でブレーキが効かなくなる
- 繰り返すことで、脳に新しい回路ができる
こうした脳のメカニズムを知ると、目の前の行動が「問題」ではなく「発達の通過点」に見えてきます。
そして、親としての関わり方も変わってきます。
「なんでできないの!」ではなく、
「まだ脳が工事中なんだね。一緒に新しい道を作ろうね」
そんなふうに、焦らず見守ることができるようになります。
さらに深く学びたい方へ
この記事では、脳科学の視点から「なぜ手が出るのか」を解説しました。
「じゃあ、実際にどう関わればいいの?」 「うちの子の場合、具体的にどうすれば?」
そんな疑問には、noteで公開している記事でお答えしています。
ぜひ、noteの記事も合わせてご覧ください。
脳の発達を理解することで、子育てがもっと楽に、もっと楽しくなりますように。
ゆうたま
※この記事が役に立ったと思ったら、SNSでシェアしていただけると嬉しいです。一人でも多くの「困っている親御さん」に届きますように。
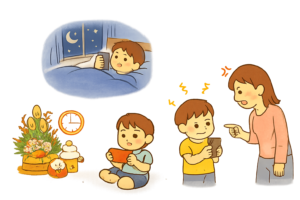



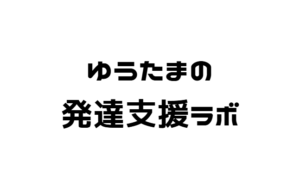
コメント