「これ、ちょっと貸してあげて」
そう声をかけた瞬間、ギュッとおもちゃを抱きしめて「僕の!」と叫ぶわが子。弟や妹が近づくだけで警戒モード全開。たとえ使っていないおもちゃでも、触られそうになると猛ダッシュで取り返しに行く…。
毎日何度も繰り返される光景に、「どうしてこんなに貸せないの?」「わがままに育ててしまったのかな」と悩んでいませんか。
今日は、子どもが「貸せない」理由と、パパ・ママができる基本的な向き合い方についてお話しします。
この記事はこんな方におすすめです
- 兄弟間でおもちゃの取り合いが絶えない
- 「僕の!」「私の!」が口癖になっている
- 共有や順番の概念がまったく通じない
- 所有欲が強すぎるのではと心配している
- 毎日の取り合いの仲裁に疲れている
「僕の!」は成長の証。所有概念が育つ時期
2〜4歳は「自分のもの」を理解する大切な時期
まず知っておいてほしいのは、2〜4歳頃の「僕の!」は、発達のごく自然なプロセスだということ。
この時期、子どもは「自分」と「他人」の境界線を理解し始めます。「これは僕のもの」「あれはママのもの」という所有の概念が育つのは、自我が芽生えている証拠。つまり、健全に育っているからこその言動なんです。
赤ちゃんの頃は、自分と周りの境界線があいまいでした。でもこの時期になると、ようやく「自分」というものが分かってきます。
ただ、この時期はまだ「自分のもの」が確立されたばかり。だから不安定で、「自分のもの」を守ろうとする気持ちがとても強く出ます。
兄弟がいると「守りたい気持ち」が加速する
一人っ子なら、家の中のおもちゃはすべて「自分のもの」として安心できます。でも兄弟がいると状況が違ってきます。
兄弟がいる子が日々経験していること:
- 自分が大切にしていたおもちゃが、勝手に触られる
- 遊んでいる途中で横から手が伸びてくる
- 「お兄ちゃん・お姉ちゃんだから貸してあげて」と言われる
- 壊されたり、なくされたりする不安がある
こうした経験が積み重なると、「守らなきゃ!」という気持ちがより強くなります。特に上の子は、「ママやパパが下の子ばかり構っている」と感じることもあり、おもちゃが自分の存在価値や安心の証になってしまうこともあるんです。
よくある対応、実はNGかも?
NG①:「お兄ちゃん・お姉ちゃんなんだから」
よく使ってしまうこの言葉。でも、子どもにとっては:
- 「お兄ちゃん・お姉ちゃんである」ことが損だと感じる
- いつも自分が我慢する立場になってしまう
- 自分の気持ちが否定される
特に3〜5歳頃は、まだ自分自身が満たされていない時期。年齢を理由に我慢を強いられると、心の安定が崩れてしまうこともあります。
NG②:「さっきまで使ってなかったでしょ」
大人の論理では「使っていない=権利がない」かもしれません。でも子どもの所有感は違います。
- 使っていなくても「自分のもの」という感覚は続いている
- 下の子が使い始めたことで、改めて「確認したい」気持ちが湧く
- まだ大人のような論理的思考は育っていない
この指摘は、子どもにとっては「自分の気持ちが分かってもらえない」と感じる言葉になってしまいます。
NG③:無理やり貸させる
「貸しなさい!」と強制的におもちゃを取り上げる…これは最も避けたい対応です。
なぜなら:
- 「やっぱり取られた」という不安が確信に変わる
- 「自分の気持ちは無視される」という諦めや怒りが募る
- 下の子への敵対心が強まる
- 次からもっと強く抵抗するようになる
一時的に静かになるかもしれませんが、根本的な解決にはなりません。
パパ・ママができる基本的な向き合い方
基本①:まずは「僕のだよね」を認める
「僕の!」と言ったとき、すぐに「貸してあげて」と返すのではなく、まず所有の気持ちを認めてあげることが第一歩です。
具体的な声かけ例: 「そうだね、これは○○くんのだね」 「大事なおもちゃだもんね」 「今、これで遊びたいんだね」
この一言があるだけで、子どもは「自分の気持ちが分かってもらえた」と感じ、心に少し余裕が生まれます。
基本②:「貸さなくてもいい」という安心を与える
「貸してあげて」と言われると、子どもは「取られる」と感じます。取られる不安があるから、余計に手放せなくなるんです。
こんな声かけを試してみてください: 「これは○○くんのだから、今は貸さなくていいよ」 「貸したくなかったら、無理しなくていいんだよ」
「貸さなくてもいい」という安心が、皮肉なことに「貸してもいいかも」という心の余裕につながることがあります。
基本③:「自分だけの場所」を作る
兄弟で何でも共有していると、「自分のもの」がないストレスが続きます。
おすすめの方法:
- それぞれに専用の箱や引き出しを用意する
- 「○○くん専用」「△△ちゃん専用」とラベルを貼る
- その中のものは、絶対に他の人が触らないルールにする
「ここに入れておけば安全」という安心の場所があることで、それ以外のおもちゃには少し寛容になれることもあります。
「貸せない」のは一時的なもの。焦らなくて大丈夫
今、毎日のように「僕の!」と叫んでいるわが子を見て、「このままずっと人に譲れない子になってしまうのでは」と不安になるかもしれません。
でも大丈夫。「共有」や「思いやり」は、一朝一夕で身につくものではありません。
自我が育ち、自分のものが確立されて、安心できる土台があってこそ、人に譲る余裕が生まれてきます。今は、その土台を作っている最中なんです。
「僕の!」と言えることは、自分の気持ちをちゃんと表現できている証拠でもあります。その気持ちを受け止めながら、少しずつ「貸せた」経験を重ねていけば、必ず変化は訪れます。
もっと具体的な対応を知りたい方へ
今回は、「貸せない」子どもへの基本的な理解と向き合い方をお伝えしました。
でも実際の子育ての現場では、こんな疑問も湧いてきませんか?
- 取り合いの真っ最中、具体的にどう声をかけたらいい?
- 下の子が泣き続けるとき、どちらをどうフォローすればいい?
- 年齢差によって対応を変えるべき?
- 「貸せた!」を自然に引き出す環境づくりって?
- 毎日の仲裁に疲れたとき、自分の気持ちをどう整理したらいい?
こうした「もっと知りたい」にお応えするため、noteのメンバーシップ限定記事では、より実践的で具体的な内容をお届けしています。
noteメンバーシップではこんな内容が読めます
📝 場面別の具体的な対応例
- 「上の子が遊んでいるおもちゃに下の子が手を伸ばしたとき」
- 「使っていなかったおもちゃを下の子が使い始めたとき」
- 実際の会話例を交えた、明日から使える声かけ
📝 年齢差別・兄弟構成別の関わり方
- 3歳と1歳、5歳と3歳など、年齢差による対応の違い
- 実際の家庭での改善事例
- それぞれの発達段階に合わせた関わり方
📝 「貸せた!」を引き出す環境づくりの工夫
- 専用ボックス、順番カード、共有エリアの作り方
- 視覚化ツールの具体例
- 協力して遊べる環境設定
📝 パパ・ママの気持ちの整理法
- 「私の育て方が悪かったのかな」と思ったとき
- 「下の子ばかり我慢させている」と罪悪感を感じるとき
- 疲れたときの心の持ち方
机上の空論ではなく、「わかる、試してみたい」と思える実践的な内容を、できるだけ具体的にお伝えしています。
メンバーシップ記事はこちら
▼ noteメンバーシップ限定記事
「『僕の!』が止まらない子への実践ガイド〜年齢別・場面別の具体的対応集〜」
日々の子育ての「困った」に寄り添いながら、一緒に前に進んでいけたら嬉しいです。
ゆうたま
子育て中のパパ・ママが「明日からちょっと試してみよう」と思える情報を発信しています。noteでは、より詳しい実践的な内容をメンバーシップ限定でお届けしています。
▼ noteはこちら [ゆうたまの発達支援ラボ]
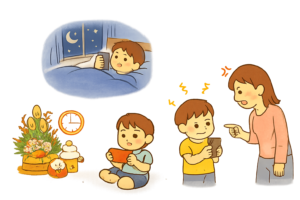



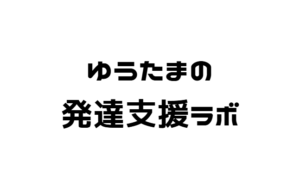
コメント